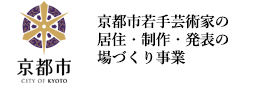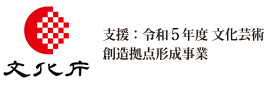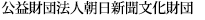みる

作品を鑑賞することは、芸術とのもっとも基本的な関わり方です。
この「みる」をより深めていくことは、あなた自身を豊かにしてくれるだけでなく、
いま生きている芸術家を支えることにも繋がります。
ここでは、「みる」をめぐるさまざまな芸術との関わり方をご紹介していきます。
0. はじめに ―現代美術をみる
1. 美術館に行く
2. ギャラリーに行く
3. 学ぶ、調べる
4. 制作者の現場に触れる
5. (作品を買う)
6. (さらに「みる」)
変更履歴
このページはみなさんのご意見を参考にし、他団体の協力を得ながら、増補・改訂を重ねて完成を目指します。
2012年5月1日 HAPS公開
2012年5月17日 HAPS改訂
2013年1月15日 「HAPSと考える展覧会鑑賞術」(2012年9月22,23日実施)参加者意見を追加
ガイドを読んで頂いた上で、「みる」ことに関して具体的なご相談をお持ちの方は下記までお願い致します。
内容によってご対応しかねる場合もありますのでご了承ください。
そういった表現に、わたしたちはどのように向き合えば良いのでしょうか。未知の表現や実験的な作品を受け入れることに、抵抗があるのは事実です。なんとなく自分のわかる範囲だけ取り入れる人もいれば、わからないことに不安を感じる人もいます。
しかし、ここではもう一歩前に進むことをお勧めします。かつて、社会のありかた、人間の考え方が変わっていかなければならなかった時代に、若い芸術家たちは大きな役割を果たしてきました。現在の、この困難な状況こそ、現代美術への理解が深まるチャンスなのです。
その最も単純で、基本的な方法が、そういった新しい作品や活動を「みる」ということです。しっかりと「みる」。自分が簡単に納得できる範囲を踏み越えて「みる」。その勇気が、生きている実感に変わる瞬間が「鑑賞」の醍醐味だといえるでしょう。
▲
1美術館に行く
まずは、美術館に行きましょう。近代から現代にかけての作品をあつかった展覧会に足を運んでください。以下にいくつか鑑賞方法を列記します。どれか一つではなく、複数を同時に試してみてください。自分なりの方法を試みても構いません。一人一人の鑑賞スタイルは異なって当然です。専門家の意見や周囲の目に流されないことが大切です。

○ 先に展覧会に関係する予備知識を得ておく。
○ まったく何も考えず、2時間暇ができたら、パッと行く。
○ 展覧会場に入る前に深呼吸をする。
○ 入口から展覧会場全体をぼーっと眺める。
○ 音声ガイドを使用する。
○ 音声ガイドはあえて使用しない。
○ 可能なかぎりゆっくりと展覧会場をまわる。
○ 個々の作品をみないで、まずは展覧会場を一周する。
○ 展覧会場を二周以上まわる。
○ 複数人で展覧会を一緒に回り、全ての作品についてそのつど感想をいう。
○ 1日かけて鑑賞ツアーを組む。
○ 歩いていて気になったところに入る。
○ 予備知識を得ずに行く。
○ 信頼する人におすすめの展覧会を聞く。
○ 一周まわって気になったものを再度みる。
○ 他の鑑賞者の話を聞く。
○ 気になった作品からみる。
○ なんとなく苦手な作品からみる。
○ 作品をみる順番によって、見終わったあとの印象に違いがあるか試してみる。
○ 友人と一緒にみに行き、別々でみる。後で感想を話し合う。
○ 空間や建築が好きな美術館やギャラリーを訪ねる。
○ 体力のある日に行く。
○ 街をフラフラしている時に入る。
○ 学芸員を呼び出す。
○ 逆まわりしてみる。
○ 可能なら中庭に出てみたり、展示とは関係のないスペースに行ったりしてブレイクを設ける。
○ なぜその展覧会に行きたいと思ったのかを考える。
○ 行く前にtwitter等で「○○の展覧会に行く」と周囲に伝えてテンションを高める。
○ 行った人の感想を聞く。その人がどうしてそう感じたのか考えてみる。
○ 作品をなるべく遠くからみる。
○ 作品との適度な距離を自分なりに決め、そこからみる。
○ スケッチブックと鉛筆を持ち込み、作品を模写する。
○ 撮影可能な場合、その作品を最高の出来映えで撮影できるポイントを探す。
○ 制作者にインタビューできるとしたら何を聞きたいか考えてみる。
○ 作品のキャプション(タイトルや解説等の表示)を読む。
○ 同じ作者の他の作品と比較する。
○ 同じテーマの他の作品と比較する。
○ 同じ素材や技術を用いた他の作品と比較する。
○ 同じ年代・地域の他の作品と比較する。
○ 作品のまわりの要素(額縁、台座など)に注目してみる。
○ 作品の厚みに注目してみる。
○ 人物画の場合、誰に似ているか考えてみる(想像する)。
○ 値段を予想してみる。
○ 自分の家に飾るとしたらどこがよいか想像する。
○ ただ飾るのではない使い道を考える。
○ 絵の中に入ったと仮定してみる。
○ 絵に合う音楽を考える。
○ 制作中の作家の心理状態を想像してみる。
○ 作者はどんな人物か想像してみる。
○ 作者に話しかけてみる。
○ どのくらいの時間をかけてできたものか想像してみる。
○ ボーっとみる。
○ ベンチがある場合、座って作品をみる。可能なら寝ころんで作品をみる。
○ 映像作品や動く作品の場合、すべてみる。
○ 風や音、リズムを聞く。
○ 作品と同じポーズをする。
○ 触れるものは触る。
○ 作家のこれまで作った作品から今回の作品へのプロセスを想像する。
○ 作者の意図と意図してない行為のラインを考えてみる。
○ 作品をみている人をみる。
○ 別の場所に置かれているところを想像する。
○ 作品を文章で書き表してみる。
○ 作品の並び順の意味を考える。
○ 作品と作品のあいだの距離について考える。
○ 照明の明るさ、色、大きさ、角度に着目する。
○ 元々の壁と新しい壁を見分けてみる。
○ 作品をみている他の観客の反応を観察する。
○ 展覧会のカタログをよく読む。
○ 内容に対して、会期と入場料が適当か考える。
○ 自分だったらどこに置くか、作品の配置を考えてみる。
○ 会場マップに自分の考えた配置を書きこむ。
○ 別の展示方法がないか検討してみる。
○ 講演会やイベントに参加する。
○ 監視員さんに質問する。
○ 特殊な場所の場合、なぜこの場所を会場に選んだのか考える。
○ お客さんがいない場合、なぜいないのか考える。
○ 個展の場合、作者の人生の変遷を想像してみる。
○ キャプションがあるかチェックする。ある場合は素材などを確認する。
○ 個々の作品の影の様子をみる。
○ 展覧会場の最初にある長い文章を最後に読む。
○ 展覧会コンセプトと各展示作品との関係性を考える。
○ 個展の場合、作品の制作年と作者の人生で起きたことを対比しながら作品の変化や流れをみる。
○ 新発見を探す。
○ 心に残った作品の作者とタイトルを思い出す。
○ 知人に来場を勧めるとしたらなんと言うか考える。また実際に勧めてみる。
○ 別の天気、別の気持ち、別の人と一緒になど、状況を変えてもう一回みにくる。
○ 感想や意見をtwitterでつぶやく。
その際、わからなかった、ピンとこなかった、いまいちだったなどと書かない。
わかったこと、感じたことを誠実に書く。
○ 展覧会直後の気持ちを、文章、ドローイング、写真などで表現してみる。
○ 展覧会のカタログ、関連する図書などを読んでみる。
○ みた展覧会と似た内容の展覧会、同じ芸術家を紹介した展覧会が過去にあったかどうか調べる。
○ 作者に会ったらどんなことを聞きたいか、伝えたいかを書き留めておく。
○ あらためて体調の良い時/悪い時に行って感じ方の違いを楽しむ。
○ 好きな作品を最後にもう一度みにいき、やはりそれが好きなことを納得する。
○ 近くのカフェやレストランに行き、味覚で記憶しておく。
○ その展覧会について書いた他の人のblog、twitter、SNS等を読む。
○ その展覧会についての専門家のレビューを読む。
○ 持って帰れるものはもらう(DM、フライヤーなど)。
○ 好きだった芸術家の過去の作品を調べる。
○ blogに展覧会の感想をまとめる。
○ ミュージアムショップに寄る。
2ギャラリーに行く
ギャラリーには、大きく商業ギャラリーと貸しギャラリーの二つがあるのですが、ここではどちらでも構いません。ギャラリーで作品を見る場合、1と同じ方法の多くが適用できると思いますが、ギャラリーならではの見方もあります。とりわけ大きな特徴は、その芸術家本人や、本人のことを良く知っている人がその場にいる可能性が高い、ということです。以下に列記しますので、是非試してみてください。
○ ギャラリーの人に作品について聞いてみる(素材、技術、コンセプトなど)。
○ ギャラリーの人に芸術家について聞いてみる(経歴、姿勢、主題など)。
○ 芸術家がそこにいる場合、質問や感想を伝える。
○ ポートフォリオ*をよく読む。
○ オープニング**の日に赴き、芸術家やその周囲の人たちと交流を深める。
○ 欲しいと思った作品を買えるかどうか聞く。その値段を知る。
○ とにかく全ての作品の値段を確認する。
○ そのギャラリーが気に入ったなら、芳名帳に記入し、リピーターになる。
○ その作品を自分の家に飾るとしたらどこがよいか想像する。
○ ギャラリーのカードやDMをもらう。
○ 好きな作品を展示しているギャラリーは、他の展覧会や取扱いの芸術家の作品もチェックする。
○ 先に作品の値段を自分でつけてみて、作品リストの価格と比較する。
▲

ポートフォリオ*
○ 生年、出身地、居住地、出身校など
○ 展覧会歴・受賞歴
○ 関連記事、評論文など
○ アーティストのステイトメント(作品のテーマやコンセプトなどの説明)
○ 作品写真
オープニング**
3学ぶ/調べる
京都市内には四つの美術系大学があります。社会人入学や、社会人向けの講座を開催している学校もあります。
京都の芸術情報を独自の視点で提供するウェブサイトもいくつかあります。
美術に関する定期刊行物はその時々の現代美術の動向を理解する助けになるでしょう。
WEB上のデータベースやアーカイヴを有効に活用することで、芸術家やその作品の背景を詳しく調べることもできます。
余裕のある方は是非海外にも目を向けてください。
また、最後にHAPSがお勧めする入門書もご紹介します。
美術手帖(美術出版社)
芸術新潮(新潮社)
美術の窓(生活の友社)
アートコレクター(生活の友社)
月刊美術(実業之日本社)
月刊ギャラリー(ギャラリーステーション)
ミュゼ(アム・プロモーション)
REAR(リア制作室)
artscape
artgene
ARTiT
tagboat/TOKYO ART GUIDE
Tokyo Art Beat
art-index
芸力
Artholic
PEELER
HAPSがお勧めする「みる」ための本
今道友信『美について』(講談社現代新書、1973年)
若林直樹『退屈な美術史をやめるための長い長い人類の歴史』(河出書房新社、2000年)
フィルムアート社 + プラクティカ・ネットワーク編『アート・リテラシー入門』(フィルムアート社、2004年)
佐々木健一『美学への招待』(中央公論新社、2004年)
岡崎乾二郎『芸術の設計 – 見る/作ることのアプリケーション』(フィルムアート社、2007年)
多木浩二・藤枝晃雄編『日本近現代美術史事典』(東京書籍、2007年)
辛美沙『アート・インダストリー』(美学出版、2008年)
暮沢剛巳『現代アート ナナメ読み』(東京書籍、2008年)
サラ・ソーントン『現代アートの舞台裏』(武田ランダムハウスジャパン、2009年)
北沢憲昭『眼の神殿 – 「美術」受容史ノート』(ブリュッケ、2010年)
椹木野衣『反・アート・入門』(幻冬舎、2010年)
杉田敦『アートで生きる』(美術出版社、2010年)
山下裕二『日本美術の20世紀』(晶文社、2003年)
夏目漱石『草枕』(新潮社、初版1914年)
▲
4制作者の現場に触れる
ちなみにニューヨーク近代美術館PS1ではインターネット上でスタジオ訪問気分が味わえるサイトを公開しています。
リンク→http://momaps1.org/studio-visit/
▲
5作品を買う
Under construction…
6さらに「みる」
Under construction…